「暮らしを切らさないという備え -空き家活用と仮設住宅の未来像-」

みなさん、こんにちは。
地方と都会に二分の一住むという選択
ココトココ事務局です。
急速な人口減少化と大規模災害が常態化する日本において、今、私たちが見直すべきは「有事に備える」という一点の対応力ではなく、「暮らしそのものの構造をどう継続可能なものにしていくか」という視点だと考えます。
■「ふるさと回帰型」仮設住宅が拓いた可能性
2024年の能登半島地震において、被災地に建設された「ふるさと回帰型」と呼ばれる新たな仮設住宅が注目を集めました。これは、従来のプレハブ型とは異なり、地域の風土や文化に即した木造戸建住宅として整備されたものです。私たちの調査の結果、入居者の評価はきわめて高く、「狭さなど生活上の制約はあるものの、居住性能や快適性に満足している」との声が多く聞かれました。特に、断熱性・遮音性・気密性の高さは、避難生活における心理的安定に大きく寄与しています。多くの入居者がそのまま継続して住むことを希望しており、これは仮設住宅が単なる「一時的な避難施設」ではなく、地域社会への再定住と生活再建の足がかりとなることを意味しています。このような事例は、「暮らしの連続性」と「地域の再生力」とを両立し得る、新たな復興住宅のモデルとして、将来の災害復興政策に重要な示唆を与えています。

※石川県珠洲市にある建設型仮設住宅「ふるさと回帰型モデル」
■拡張の鍵は「空き家」の平時活用
とはいえ、「ふるさと回帰型」の全国的な普及には、土地の確保や建設人材の不足といった制約も存在し実際に導入件数は33戸で全体の0.4%程度に限定されています。特に能登半島地震でも課題となったように、復旧・復興には多くの時間と資源を要するため、その間、被災者の暮らしをどう支えるかが問われています。そこで浮上するのが、平時から地域に存在する空き家の利活用という視点です。その具体例として、能登半島地震では、Airbnbを通じて延べ1,000人以上、30〜40組の家族が民泊に避難しました。これは既存の民泊施設を活用し、有事には迅速に避難所として転用するという、新しい形の減災モデルと言えます。このような仕組みを、単なる「一時避難」にとどまらず、みなし仮設住宅へのスムーズな移行へと繋がり、長期的な生活基盤の提供への拡大展開が可能です。つまり、「空き家 → 民泊(平時) → 避難所(有事) → 仮設的居住(復興期)」という生活の連続性が、制度として設計できる可能性が見えてきたと言えます。

※里山ハウス「ココサト」は空き家を民泊利用し、有事に避難所やみなし仮設に移行するイメージを持って運営しています。
■「備える社会」から「つなげる社会」へ
今、私たちは「備える社会」から、「暮らしをつなげていく社会」への転換点に立っています。災害を特別な出来事と捉えるのではなく、日常の延長線上で、柔軟に・持続的に対応できる暮らしのあり方こそ、次世代の減災モデルと言えるのではないでしょうか。増え続ける空き家と、災害リスクの高まる社会。この二つの課題を統合的に捉え、暮らしの回路を切らさない仕組みこそが、これからの地域防災の鍵になるはずです。
ご相談、質問などございましたら
「ココトココ」事務局までご相談ください。
「二拠点」経験者が、お話を伺います。
コメント ( 0 )
トラックバックは利用できません。








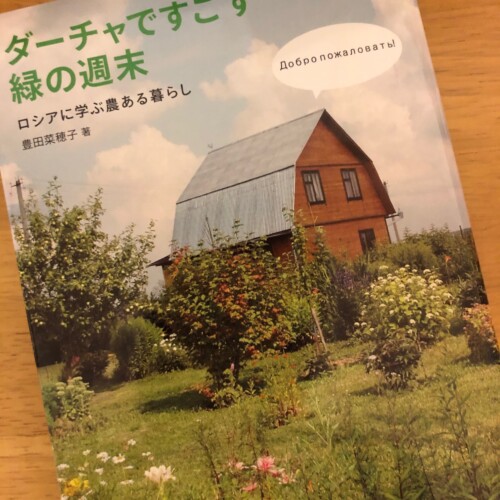

この記事へのコメントはありません。