持続可能な生活圏の形成を目指して-地域×大学×企業の取り組み-

みなさん、こんにちは。
地方と都会に二分の一住むという選択
ココトココ事務局です。
関西学院大学 人間福祉学部 社会起業学科 石田祐教授のゼミに所属する大学生たちが、西脇市芳田地区にフィールドワークに来てくれることになりました。月1~2回ほど定期的に芳田地区に泊まりこみ、地域課題を解決するためのプロジェクトを展開していく予定です。ちなみに、今回の取り組みは、兵庫県が持続可能な生活圏の形成を目指し、地域の活動団体が大学と企業等と連携して取り組む「地域×大学×企業のひょうご絆プロジェクト」として動いています。また、それとは別に、関西学院大学と西脇市が包括連携協定を締結しています。
地域×大学×企業のひょうご絆プロジェクト
https://web.pref.hyogo.lg.jp/kk08/chiikisouseikyoten2.html

地域×大学×企業の連携先の1つで、神戸マツダ様もご参加いただいています。地域の足に車は欠かせません。車両関係のご支援も頂戴しています。

そのような中、6月から若い男性が1名、芳田地区に1か月間、住み込みすることになりました。その名は、江口はると君。現在4回生の彼は高知県土佐清水市出身。郷土愛に溢れ、いずれ土佐清水市に戻って地域に貢献したい志を持つ青年です。

土佐清水市といえば、高知県の西南部に位置する四国の西南端の場所。アメリカ合衆国を訪れた最初の日本人の一人であり、明治維新の礎を築いたジョン万次郎が生まれた場所です。足摺沖の好漁場と風光明媚な自然美を有する、漁業と観光のまちで、一度、訪れたことがありますが、足摺岬から見る太平洋の雄大さは、言葉では表せないほど広大で美しい場所です。その土佐清水市の総人口は10,768人(推計人口、2025年5月1日)。令和3年3月末で65歳以上の高齢者比率は50.0%を超えています。江口君のような若者のチカラは、地域にとっては欠かせない存在となるでしょう。
そのような江口君の滞在を皮切りに、学生が芳田地区に何ども足を運んでいただき、地域との打ち合わせや地域課題の実践活動に体験。また、時には楽しみも必要なので、田植え体験やホタル観賞等を行いました。(笑)

こちらは学生たちが考えた地域課題案について地域住民との意見交換の様子です。

人口減少化も背景に、年々増え続ける空き家の対策を地域で実施しています。空き家管理の1つとして、草刈り体験も行いました。

放置竹林も課題です。竹林を資源に変えていこうと、竹藪整備とカブトムシの養殖場づくりの活動にも参加してもらいました。

地域の田植えにも参加。自分たちで植えたお米を食べる時が楽しみにで仕方ないでしょう。それにしてもおにぎりがでかすぎる(笑)

5・6月の体験を踏まえて、学生主体のプロジェクトが、今後も進んでいくことになります。地域出身の高校生・大学生は、学業や就職の兼ね合いで、地域外に出てしまいます。しかしながら、このような地域に縁がなかった大学生が逆流してくれる流れは、地域側にとって、とても新鮮で有難いことです。持続可能な生活圏の形成を目指し、地域の活動団体と大学と企業等が連携して取り組むプロジェクト。多様な関わりと地道な継続のチカラから生まれるウェルビーイングな今後の展開が楽しみです。
ご相談、質問などございましたら
「ココトココ」事務局までご相談ください。
「二拠点」経験者が、お話を伺います。
コメント ( 0 )
トラックバックは利用できません。


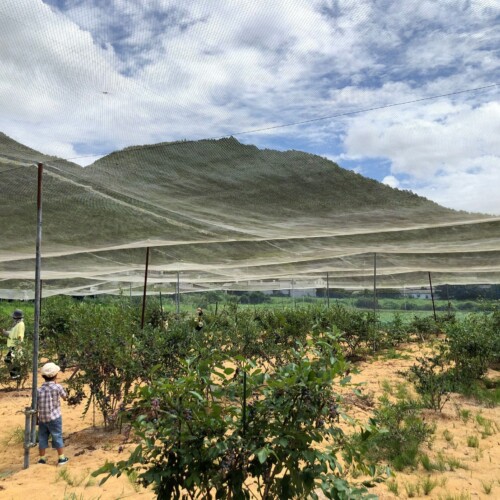







この記事へのコメントはありません。